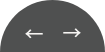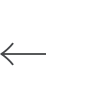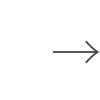KENBO co.,ltd. All Rights Reserved.
S造(鉄骨造)住宅の要の鉄骨!理解を深めてより良い家にしよう
鉄骨造について理解しよう
鉄骨造住宅は、その名のとおり鉄骨を骨組みとして利用してつくられた住宅のことをいい、S(steel・・・鋼鉄)造と略して呼ばれることもあります。
鉄骨の種類は「重量鉄骨」「軽量鉄骨」などがあり、さらに、鉄骨造の家はたくさんの工法があり、それぞれのメリットデメリットも存在します。
鉄骨造の家についてここで詳しくご紹介しますので、一緒に学んでいきましょう。
鉄骨の分類方法のいろいろ

鉄骨には分類方法がいろいろあります。
厚みでの分類は以下です。
・軽量鉄骨:厚さ6mm未満の鋼材、鉄板を曲げて作ったもの
特徴:地盤に大きな問題がない、間口の狭い土地に適する、大手ハウスメーカーの鉄骨の家で多い造り
・重量鉄骨:厚さ6mm以上(一般的な厚みは9mm、12mm)の鋼材
特徴:柱が少なくてすむ、間取りの自由度が高まる、軽量鉄骨よりも家づくりのデザインの幅が広まる、地盤が非常に硬くて耐地力のある場所で建てられる、鉄骨が重いため地盤を強くする必要があり基礎工事の費用が高くなる
他にもH鋼、I鋼など、鉄骨の形で分類する方法もあります。
鉄骨造の工法のいろいろ

鉄骨造住宅の工法についてご紹介します。
・ブレース工法(鉄骨軸組工法)
:木造在来工法(木造軸組工法)と同じ、鉄骨の柱・梁・筋交いを使った工法
・ラーメン工法
:柱と梁を接合した構造、筋交いが不要なほど頑丈な構造、大量生産された材料を使って組み立てる、精度や品質は安定しているのがメリット、デメリットは自由度が低くリフォームや増改築での選択肢が狭まること
・プレハブ工法(鉄骨ユニット工法)
:工場で溶接してつくり、現場でボルトとナットなどで組み立てる工法
狭い道での搬入が難しい(ユニットパネルを運ぶため)
鉄骨造の断熱は外断熱が良し
断熱材の貼り方には2種類あります。
内断熱:外壁の内側に貼る方法
断熱材基準の厚みは薄くてもOK
防結対策が厳しい
熱橋(外壁と内壁の間にある部分)で熱が通り抜けてしまう
外断熱:外側から断熱材を貼る方法
断熱材基準が厳しい
防結対策は緩い
建物が断熱材で覆われているため、熱が通り抜ける心配がない
上記のことから、外断熱だと熱が逃げにくいこともあり、鉄骨造住宅に適しているといえます。
家のプロに鉄骨造について聞いてみよう
鉄骨造について、少しでも理解が深まったでしょうか?
ただ、自分の家と考えた場合鉄骨造の家が果たして最適なのかどうかはなかなか判断がつかないものです。
鉄骨造は、耐火性・耐震性に優れ、木造住宅よりも丈夫です。
ですので、家の丈夫さや耐火性・耐震性を特に重要視する方にとっては鉄骨の家はおすすめといえるでしょう。
また、工場で材料がほとんどつくられるため工期が短くすみます。
木造住宅では約半年以上かかりますが、鉄骨造では重量・軽量どちらでも約4ヶ月ほどの後期で済むのです。
ただ、鉄骨造にもデメリットがあります。
例えば、鉄骨は熱が当たると柔らかくなって曲がってしまったり、湿気に弱いため雨によって錆びてしまうなどのリスクもあります。
そのため、耐火被覆材の鉄骨を使ったり、防錆処理が出来ている鉄骨を使うことが大切です。
さらにデメリットを挙げると、鉄骨造住宅は夏は暑くて冬は寒いため、冷暖房効率が悪くなり、ランニングコストが多くかかる可能性もあるのです。
丈夫さでいうと鉄骨造はとても魅力的に見えますが、その他のデメリットや特徴などをしっかりと把握した上で自分たちの家として採用するかどうかを見極めるようにしましょう。
ただ、専門的な知識が多く必要なのも鉄骨造の特徴でもありますので、住宅のプロに相談してみることをおすすめします。
鉄骨造住宅について、建房にご相談いただけましたら、なんでもお答えしますよ。
まとめ
鉄骨造住宅には様々な特徴がありますが、施工業者によって材質や工法にも違いがあるため、そこでも様々なメリットデメリットが出てきます。
鉄骨造をご検討されている方は、色々な工法や鉄骨の材質などを勉強して自分たちにあった住宅を探すようにしましょう。
建房では、お施主様の要望を盛り込んだ家づくりができるよう、話し合いをしながら進めております。
また、困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!
RECOMMEND